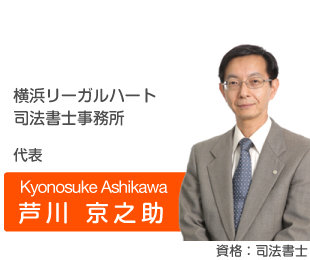不動産売買登記の必要書類(買主・売主)
不動産売買登記の買主
通常の場合
不動産売買登記の名義変更に必要な買主の書類と印鑑は、次のとおりです。
法務局の職権による住所氏名変更登記の方法(令和8年4月1日から開始)を参考にしてください。
- 住民票1通(個人・自然人)
同一世帯の買主が複数で不動産を購入する場合、同一世帯の場合は世帯全員の記載された住民票1通で可。
海外在住外国人の場合は、外国に居住する外国人(外国籍)の住所証明情報(住所証明書)を参考にしてください。 - 印鑑証明書(住宅ローンがある場合)(市区町村発行の3か月以内のもの)1通
- 身分証明書
運転免許証、市区町村発行の公的個人認証カードなど公的な機関発行の写真付きのもの
写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険証など2点が必要です。 - 印鑑は、認印でも結構です。ただし、住宅ローンがある場合は実印
- 海外に在住する日本人・外国人が買主となる場合は、次を参考にしてください。
海外在住の日本人(日本国籍)・外国人(外国籍)が不動産を取得したときは、「国内連絡先(日本国内における連絡先となる人)」の登記が必要です。これについては、「日本国内における連絡先となる人」の登記の方法(令和6年4月1日施行)を参考にしてください。
外国人が所有権の登記をするときの氏名:ローマ字で氏名を併記する(令和6年4月1日から)
海外在住日本人の所有権移転・抵当権設定登記(必要書類)
海外在住日本人の住宅購入(家族が日本に住んでいる場合) - 買主が会社の場合、会社登記記録情報
会社法人等番号を登記する。(令和6年4月1日施行)
法人の本店・商号の後に
(例)「会社法人等番号 0100-01-123456
添付情報として、「法人識別事項を証する情報」を記載する。
他の共有者の持分の取得に係る登記の添付情報
法人識別事項が既に登記されている所有権の登記名義人における他の共有者の持分の取得に係る所有権の移転の登記を申請する場合において、当該法人識別事項を申請情報の内容としたときは、
「法人識別事項を証する情報(省略)」の例によりその旨を明らかにするものとする。
外国に居住する外国人(外国籍)の住所証明情報(住所証明書)
外国に居住する外国人(外国籍)の住所証明情報(住所証明書)は、令和6年4月1日から次の取り扱いとなります。(法務省通達)
次の(1)または(2)のいずれかの住所証明書が必要です。(外国語は日本語への翻訳が必要)
(1)登記名義人となる者の本国または居住国(本国又は居住国の州その他地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証する書面(これと同視できるものを含む。(?「政府」と「地方の役所」とは異なる。)← 公証人の証明書(宣誓陳述書)のみは認められない。 政府(本国等の領事を含む)発行の住所証明書は、通常ないと思われる。 そこで、次の公証人作成の住所証明書とパスポート(政府発行の身分証明書と上申書)コピーで対応することになると思われる。 (2)登記名義人となる者の本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面で行う場合は、次のアまたはイの書面を併せて提出する。 ア:登記名義人となる者が旅券(パスワード)を所持しているとき 次のすべての要件を満たす旅券の写し(パスポートのコピー) ① 住所を証明する書面が公証人作成日において有効な旅券(有効期間のあるパスポート) ② 登記名義人となる者の氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示 ③ 当該住所を証明する書面と一体となっていない旅券の写しにあっては、原本と相違がない旨の記載と登記名義人となる者の署名又は記名押印 イ:登記名義人となる者が旅券を所持していないとき 登記名義人となる者の作成に係る旅券を所持していない旨の上申書及び登記名義人となる者の本国等政府の作成に係る書面(政府発行の身分証明書)又は電磁的記録(以下「書面等」という。)の写し等(写し又は電磁的記録の内容を書面に出力したも のをいう。以下同じ。)であって、次の要件を満たすもの ① 登記名義人となる者の氏名の記載又は記録がある書面等の写し等であること。 ② 当該住所を証明する書面が作成された日又は当該申請の受付の日において有効な書面等の写し等であること。 ③ 当該住所を証明する書面と一体となっていない書面等の写し等にあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。
外国に住所がある法人(会社)の住所証明情報(住所証明書)
外国に住所がある法人(会社)の住所証明情報(住所証明書)は、令和6年4月1日から次の取り扱いとなります。(法務省通達)
次の(1)または(2)のいずれかの住所証明書が必要です。(外国語は日本語への翻訳が必要)
(1) 登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。)
↓
法人(会社)登記簿がこれに該当すると思われる。
法人(会社)登記簿がない場合
(2) 登記名義人となる者の本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面及び次のア又はイに掲げる区分に応じ当該ア又はイに定める書面
ア:登記名義人となる者が旅券を所持しているとき次の要件を満たす旅券の写し
① 当該住所を証明する書面が作成された日又は当該申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
② 登記名義人となる者の氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
③ 当該住所を証明する書面と一体となっていない旅券の写しにあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。
イ:登記名義人となる者が旅券を所持していないとき登記名義人となる者の作成に係る旅券を所持していない旨の上申書及び登記名義人となる者の本国等政府の作成に係る書面又は電磁的記録(以下「書面等」という。)の写し等(写し又は電磁的記録の内容を書面に出力したものをいう。以下同じ。)であって、次の要件を満たすもの
① 登記名義人となる者の氏名の記載又は記録がある書面等の写し等であること。
② 当該住所を証明する書面が作成された日又は当該申請の受付の日において有効な書面等の写し等であること。
③ 当該住所を証明する書面と一体となっていない書面等の写し等にあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。
買主が未成年者
上記通常必要な書類と印鑑のほかに、次の書類が必要となります。
未成年者に代わり親権者が署名、捺印しますので、未成年者の親権者であることを証明します。
- 戸籍謄本(市区町村発行の3か月以内のもの)1通
- 住民票(本籍などすべて記載されたもの)1通
不動産売買登記の売主
不動産売買登記の名義変更に必要な売主の書類と印鑑は、次のとおりです。
通常の場合
- 権利証
売主となる人が不動産の名義人となったときに登記所から発行された登記済権利証または登記識別情報
登記済権利証か登記識別情報かは、登記所から発行された時期によって異なります。
その他、「権利証」については、次を参考にしてください。
不動産売買登記と権利証(一般的な説明)
不動産売買登記と権利証(合筆登記)
不動産売買登記と権利証(分筆登記)
権利証がない場合
不動産売買登記と複数の権利証が必要な場合
不動産売買登記と権利証がない場合(債権者代位登記)
不動産売買登記と権利証・登記事項証明書の違い - 印鑑証明書(市区町村発行の3か月以内のもの)1通
海外在住の日本人が売主となる場合は、海外在住日本人の住宅売却(必要書類)を参考にしてください。 - 住民票1通
「登記されている住所」と「現在の住所」が異なる場合は、登記名義人の住所変更が必要です。
住所が転々と変更されている場合には、基本的に、すべての住所のつながりを証明する必要があります。
住所が転々と変更されている場合で、住所の変更を証明することができない場合は、
次の書類などが必要となりますので、登記手続を依頼する司法書士にご確認ください。
1)不在籍不在住証明書
2)上申書
その他、「住所変更証明書」については、次を参考にしてください。
不動産売買登記と住所変更登記(売主)
不動産売買登記と住居表示変更による住所変更登記
不動産売買登記と町名地番変更による住所変更登記
不動産売買登記と行政区画の変更
海外在住の方は、日本「国内における連絡先」を登記する必要があります。海外在住日本人の住所変更登記を参考にしてください。 - 評価証明書
評価証明書は、各市区町村の固定資産税課で取得します。
東京23区の場合は、都税事務所の固定資産税課で取得します。
固定資産に関する証明書のうち、公課証明書は固定資産税、都市計画税(不動産業者は固都税と呼んでいます。)が記載されます。これは、固都税(ことぜい)の精算のために必要となります。
評価証明書は、所有権移転登記の登録免許税を計算するために必要です。
所有権移転登記の登録免許税は、評価証明書に記載された評価価格で計算します。(課税価格ではありません。)
そのため、公課証明書でも代用できます。公課証明書にも評価価格が記載されています。 - 身分証明書
運転免許証、市区町村発行の公的個人認証カードなど公的な機関発行の写真付きのもの
写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険証など2点が必要です。 - 実印
- 抹消登記すべき権利の抹消登記書類
例えば、売主が不動産を取得する際、住宅ローンで購入した場合、抵当権が設定登記されている場合は、この抵当権を抹消登記する必要があります。
売主が買主から受け取る売買代金で住宅ローンを返済する場合、通常、売買の決済後に、抵当権抹消登記書類を金融機関に受け取りに行きます。
その他、「抹消登記」については、次を参考にしてください。
不動産売買登記と売主の抵当権抹消登記
不動産売買登記と売主の担保の抹消登記
不動産売買登記と売主の差押の抹消登記
不動産売買登記と売主業者の抵当権の効力の縮減
不動産売買登記と任意売却(国民健康保険料の滞納)
売主が未成年者(親権者)
上記通常必要な書類と印鑑のほかに、次の書類が必要となります。
未成年者に代わり親権者が署名、捺印しますので、未成年者の親権者であることを証明します。
- 戸籍謄本(市区町村発行の3か月以内のもの)1通
- 住民票(本籍などすべて記載されたもの)1通
- 親権者の実印
- 親権者の印鑑証明書(市区町村発行の3か月以内のもの)1通
登記名義人が死亡している場合(相続登記)
上記通常必要な書類と印鑑のほかに、次の手続が必要となります。
登記名義人が死亡している場合、売買契約締結前に、相続登記をする必要があります。
相続登記に必要な書類は、相続登記情報館のサイトでご確認ください。
売主が認知症(成年後見人)
上記通常必要な書類と印鑑のほかに、次の書類が必要となります。
売主が認知症の場合は、基本的に、成年後見人が代理して、署名、捺印します。成年後見人がいない場合、家庭裁判所に成年後見開始の申し立てをし、成年後見人を選任してもらいます。
成年後見人と成年後見制度を参考にしてください。居住用の不動産を売却する場合、さらに、家庭裁判所の許可書も必要です。
- 成年後見人の成年後見登記事項証明書(登記所発行の3か月以内のもの)1通
- 成年後見人個人の印鑑証明書(市区町村発行の3か月以内のもの)1通
- 成年後見人個人の実印
- 居住用不動産の売買の場合は、家庭裁判所の売却の許可書1通
居住用不動産の売却には、家庭裁判所の許可(審判書)が必要なので、その代わり、権利証(登記済権利証・登記識別情報)を登記所に提出する必要がない。(平成29年横浜地方法務局横須賀支局で登記完了)
その他の場合は、権利証(登記済権利証・登記識別情報)が必要 - 後見監督人がいる場合は、後見監督人の同意書・印鑑証明書
売主が行方不明(不在者財産管理人)
上記通常必要な書類と印鑑のほかに、次の書類が必要となります。
売主が行方不明の場合は、不在者財産管理人が署名、捺印します。
- 不在者財産管理人の選任審判書(家庭裁判所発行の3か月以内のもの)1通
- 不在者財産管理人個人の印鑑証明書(市区町村発行の3か月以内のもの)1通
- 不在者財産管理人個人の実印
- 家庭裁判所の不動産売却の許可書1通
登記名義人が死亡(相続人不存在・相続財産管理人)
上記通常必要な書類と印鑑のほかに、次の書類が必要となります。
相続人が不存在の場合、売却するときには、相続財産管理人が署名、捺印します。
- 相続財産管理人の選任審判書(家庭裁判所発行の3か月以内のもの)1通
- 相続財産管理人個人の印鑑証明書(市区町村発行の3か月以内のもの)1通
弁護士の場合、家庭裁判所に登録の印鑑証明書でも可。(法務局に事前確認を要する。横浜地方法務局厚木支局で可。)この場合、印鑑証明書には、弁護士事務所の住所は記載されない。(横浜家庭裁判所小田原支部)
選任時から弁護士事務所が変更している場合、弁護士事務所変更証明書を添付する必要があるか。法務局に事前確認を要する。横浜地方法務局厚木支局では、弁護士会の証明書で可。(念のため参考書類として添付した。) - 相続財産管理人個人の実印
弁護士の場合、家庭裁判所に印鑑の登録をしている場合(登録申請をする。)、登録印鑑でも可。(法務局に事前確認を要する。横浜地方法務局厚木支局で可。) - 家庭裁判所の不動産売却の許可審判書1通
- 権利証は不要。

売買による所有権移転登記の前に「相続人不存在による相続財産」の登記(所有権登記名義人住所氏名変更登記)をする必要があります。「相続人不存在による相続財産」の登記の方法を参考にしてください。
登記名義人が破産(破産管財人)
上記通常必要な書類と印鑑のほかに、次の書類が必要となります。(ただし、権利証は不要です。)
不動産が破産財団に属しているときは、破産管財人弁護士が署名、押印します。
- 破産管財人弁護士の選任審判書(裁判所発行の3か月以内のもの)1通
- 破産管財人弁護士の印鑑証明書(裁判所発行の3か月以内のもの)1通
- 破産管財人弁護士の印鑑(裁判所に登録しているもの)
- 裁判所の不動産売却の許可書1通